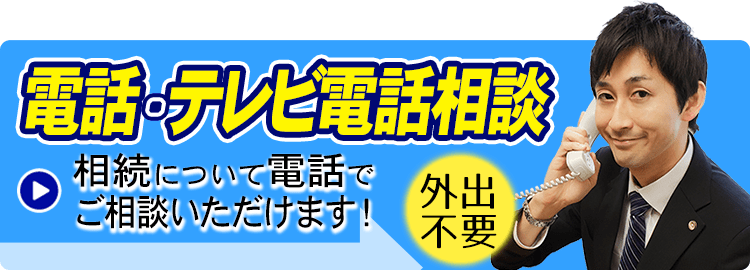連絡のとれない相続人がいた場合の対処法
1 相続人の連絡先が分からない場合
相続人に遺産分割の連絡をしようにもそもそも連絡先が分からないような場合、まずはその住所を調べる必要があります。
被相続人の戸籍をたどっていくと、連絡先が分からない相続人の現在の本籍地が分かります。
さらに戸籍の附票を取得することによって、住所を調べることができます。
住所が分かれば、手紙を出すなどして、遺産分割協議を進めていくことができます。
2 行方不明の相続人がいる場合
前記1の方法で調査しても、住民票の登録がなくなっていて、行方が分からないことがあります。
その場合は、行方不明の方(不在者)について、財産を管理してもらうため、不在者財産管理人の選任を申し立てます。
参考リンク:裁判所・不在者財産管理人選任
たとえば、家庭裁判所の許可を得て、不在者に代わって遺産分割協議を行うことができます。
または、行方不明の方を法律上死亡したものとみなして扱う失踪宣告の制度により、行方不明の方の相続手続きを行うことができます。
参考リンク:裁判所・失踪宣告
3 連絡先は分かるが連絡がとれない場合
連絡先は分かっても、心理的に連絡をとりにくい場合、連絡をしても応じてもらえないような場合など、様々な理由で、連絡がとれない場合があります。
そのような場合、交渉を弁護士に依頼して進めることができます。
それでも相手方から協力が得られない場合には、遺産分割調停の申し立てを行います。
遺産分割調停を申し立てると、家庭裁判所から相手方に対し、期日の呼出がなされます。
月に1回程度のペースで期日が設けられ、調停委員が間に入って交互に話を聞くことで、話し合いによる解決を目指していくことができます。
調停においても相手方が何ら対応せず、期日を何回も欠席するような場合は、遺産分割審判に移行し、家庭裁判所の審判官が遺産分割の方法を判断することになります。
死後事務委任契約とは|活用方法や遺言との違いなどを解説 遺産分割審判に不満・不服がある場合の即時抗告のやり方